「大規模修繕は時代遅れ?」マンション管理新発想
2025年3月、公正取引委員会はマンションの大規模修繕で数十年以上談合を繰り返してきたとして20数社に立ち入り検査を行った。大手のマンション修繕工事会社がほぼ根こそぎ公取委の検査を受けた状態だが、そもそもマンションの大規模修繕では談合が起きやすい。
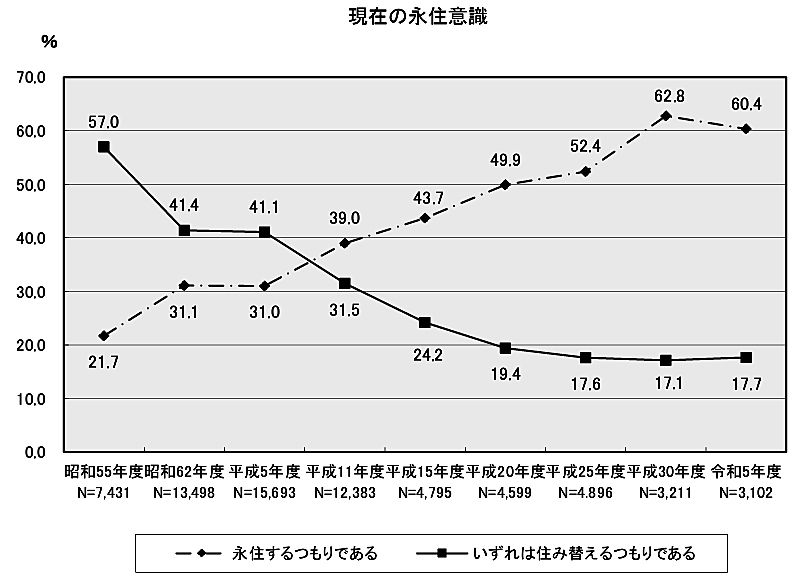
談合防止だけでなく、資産の維持、修繕積立金の安定的な運用その他を考えると大規模修繕自体が時代遅れと指摘する人たちがいる。これからは中規模修繕を目指すべきというのだ。
歴史が浅く"横のつながり"の強い大規模修繕業界
そもそも大規模修繕の業界は談合あるいは忖度しあうような環境にある、と指摘するのは株式会社KAIライフサイクルマネジメントの菅純一郎さん。
その理由のひとつは、業界そのものの歴史と成り立ちにある。
建築設備の法定検査を業務としていた菅さんが最初に大規模修繕に関する相談を受けたのは40年ほど前の昭和末期。団地で問題が生じていると言われ、相談に乗り始めたのがきっかけで以降関わりができた。初期はノウハウもコンサルできる人もなく、試行錯誤が続いていたという。
歴史のない業界の常として大規模修繕の業界でも事業者は派生、派生で増えてきた。
「A社にいた人が独立してB社、C社を始め、B社にいた人がさらにという形で事業者が増えてきた業界です。談合以前に横のつながりが強く、悪意のない忖度も含めればなんとなく価格調整が行われ続けていても不思議はありません」と菅さん。加えて談合につながりやすい慣習もある。それが事業者に相見積もりを依頼する際に設計監理を行う事業者が作る設計図書などの書類だ。規模にもよるが、この書類を作成するだけで数百万円などと費用がかかるものである。
この書類には工事の項目が細かく挙げられており、そこに記載されている数字をゼロにして各社に相見積もりを依頼するのだが、単価を入れるだけで総額が出る。その単価をちょっとずつ高くしたら総額が高くなるのは自明の理。
「大手管理会社は業者会などといった名称で大規模修繕を依頼する事業者の集まりを作っており、そこに相見積もりを依頼します。互いにどこが参加しているかがわかれば、その力関係などから受注調整などが起きる可能性は十分にありえます。全社がほんの少しずつ上振れした数字を出せば相場がいくらなのかは全くわからなくなります」
だったら、その都度違う事業者に見積もりを依頼すればいいと思うだろうが、それは現実的ではない。なんらかのビジネスをしている人ならわかるだろうが、年に何回もやる同じような仕事で毎回、ゼロベースで見積もりを依頼するのは互いに消耗するだけだ。
それに、そもそも管理会社は建物や設備に関してほとんど知識がない。目の前の建物に今の時点でどのような修繕が必要かが判断できない以上、修繕を担当する会社に「今、修繕が必要です」と言われれば言うなりになるしかない。
管理会社、管理組合と大規模修繕事業者の情報はゼロ百と言ってもよいほど非対称なのである。
加えて今はまだ業界全体がコロナ禍の影響を引きずっている。コロナ禍では大規模修繕を見合わせる管理組合が相次ぎ、制約解除以降に工事が集中。市場が過熱した。
現在はそこに人手不足、建材等の高騰が拍車をかけている。事業者を公募、見積もり取得後に工事の依頼をしても半分は断られるほどの売り手市場になっているという。
無駄な工事までやるから修繕積立金が枯渇
とはいえ、そんな状況下でもマンションの資産価値を維持するためには修繕は必要だ。
「であれば、まずは1回のスパンを15年、できれば17~18年に延ばし、さらに全部を一度にやるのではなく、目の前で必要なものだけを何度かに分けてやる、中規模修繕に切り替えればいいのです」と菅さん。
大規模修繕では足場を架けて工事をするが、足場架設に多額の費用がかかるため、それならばといろいろな修繕をこの機に一度にやろうとなりがち。そしてそこに無駄が生じる。
わかりやすいのは屋上防水。10年保証が付いているが、10年でダメになるというわけではない。
劣化の状況次第では20年近くまでは大丈夫だというが、大規模修繕の際には一緒にやってしまいましょうと提案されることが多い。それに対して反論できる管理組合はほぼなく、プロがそういうのだったらと一緒にということになる。だが、屋上防水はそもそも足場とは無縁の工事。足場を組むから一緒にという自体がおかしな話なのだが、誰もそれには気づかないまま、工事をやってしまうのである。
一度に多額を支出して修繕積立金が底をつき、値上げを検討せざるをえない状況に陥る。そうならないよう「何度かに分けて修繕したほうが収支バランスがよくなり、資産価値も維持できる」というのが株式会社佐々木設計事務所の佐々木龍郎さんだ。佐々木さんは実際、中規模修繕を実践しているマンションに居住している。
佐々木さんが住んでいるのは1971年竣工、2025年時点で築54年、全63戸の都内にあるマンション。
最初は賃貸で入居、2006年に耐震性能が低く、建て替えができないことを知りつつも購入したもので、2011年の東日本大震災で激しく揺れた。そのため、2017年に耐震補強をしたのだが、それによって修繕積立金は残り6000万円ほどまでに激減した。
「高齢の居住者が多かったので一時金を集めることが難しく、積み立ててあったお金で賄ったのですが、そうすると次に12年後に大規模修繕をするまで窓ガラスの交換ができず、寒さ、結露に耐えなくてはいけない。それはつらい、と2019年から4年ごとに中規模修繕をすることになりました」と佐々木さん。
2017年からの2年間で貯まった修繕積立金に加え、国と都、区の補助金も活用。サッシメーカーに直接依頼して全窓をカバー工法でアルミ複層サッシに交換したのだが、このやり方なら途中にワケのわからない費用は発生しない。
断熱に関しては2021年に玄関扉をやはりカバー工法で断熱扉にしており、このあたりから住民の間でも中規模修繕という考え方が根づき始めたという。改修で部屋が暖かく、結露もなくなって快適になるのだから、このやり方で良しとする人が増えるのは当然だろう。
その後、2023年には屋上防水、エレベーターの改修という比較的費用の嵩(かさ)まない修繕を実施、2027年には費用のかかる外装の更新、2031年には給排水衛生設備を更新、地下の受水槽を撤去して直接給水方式に切り替える。以降も4年ごとにその時に必要な工事を行っていく予定だという。
「4年ごとにいくら修繕積立金が貯まり、それを優先順位に合わせてどこに使う予定かという資料を管理会社に依頼、適宜相談しながら作ってもらい、住民にわかりやすく説明しています。管理組合とは別に修繕委員会を組織、工事実施2年前に招集、3年間活動してその後1年はお休みという仕組みにして、負担がかかりすぎないようにもしています」10数年に一度の大規模修繕はその間にどんと落ちた価値を大きく上げるための修繕になり、項目も費用も増える。この時しかやる機会がないからと無駄な工事もまとめてやっておこうとなる。意図せずとも談合の危険が入り込んでくる。だが、4年に一度なら物件の価値がさほど落ちないうちに次の工事が行われるので価値を維持し続けることができる。10数年マイナスがマイナスのままで劣化が進む物件より、4年ごとにどこかがプラスになり続ける物件のほうが市場価値も落ちない。
実際、立地のせいもあるが、佐々木さんの住んでいるマンションは賃貸に出してもすぐに決まり、不動産価格も購入時から2倍近くまで上昇している。
「手間・総額増」でもメリットの多い中規模修繕
もちろん、いいことばかりではない。佐々木さんのマンションのように4年に一度工事があるのは煩わしいと思う人もいるだろうし、管理組合の仕事、手間も増える。修繕積立金が少ないマンションではなかなか次の工事に必要な額が貯まらないこともありうる。
それに必ずしも中規模修繕で総工事費用が安くなるわけではないと菅さん。
「工事を分散することで工事費は明朗化しますが総額1億円が1億2000万円になることはありえます。まとめてやるほうが総額は減らせる可能性が高いのです」
それでもそれ以上にメリットは大きいと菅さん、佐々木さんはともに声をそろえる。
収支バランスがよくなる上に、災害の多い今の時代に大規模修繕で修繕積立金を使い果たしてしまうリスクが軽減できる、少しずつでもバリューアップしている物件なら空き家にもなりにくいなどのメリットが大きいからだ。
もうひとつ、佐々木さんは工事の精度も指摘する。
「今、現場では全体を見て監督する人たちが40~50代の氷河期世代にあたり、人手が足りていないだけでなく、全体が見えていない人が多い。
そのような状況なので、一度に多くの仕事を依頼するよりも足場だけ、窓だけ、設備だけと仕事を分割、場合によっては地元の工務店に依頼するなどとしたほうがいい結果になる可能性もあります」
中規模修繕実現のための障壁は意識と知識
ただ、どこの管理組合でも中規模修繕ができるかといえばそこにも問題がある。ひとつは意識の問題だ。
「東日本大震災後、危機感から耐震改修をリードした所有者がおり、その人の活動から管理会社に丸投げにして終わりではなく、自分たちで考えようという機運が生まれ始めました。
2016年に共用部の電源一括受電を全員賛成で採択、それによって年間かなりの管理費を節約できた成功体験もあり、自分たちでもできるんだと思うようになったところで私が中規模修繕を提案。やってみようかという気になったのだと思います」と佐々木さん。
マンションの管理では考える、判断するのは所有者であり、管理組合である。管理組合が主体となって管理会社を巻き込み、一緒にベストな道を探る。そんな取り組みができれば修繕のあり方を見直せるのではないかというのだ。
もうひとつ、大事なのは管理組合、管理会社に足りていない知識をどう補うか。建築や設備に詳しい所有者がいればその人が核になって行動できるだろうが、そういう人がいない場合にはどうすればいいか。
菅さんは顧問として専門家と契約すればよいという。
「大規模修繕で設計監理に多額をかけるのをやめて、その費用で常に自分たちの味方になって中立的な立場でアドバイスをしてくれる顧問を雇えばいいのです。できれば資産面でのアドバイザーと建物、設備がわかる人の2人がいれば盤石でしょう」
佐々木さんは今後、マンションに限らず、建物の維持管理に関わるアドバイスができる中立的な組織が必要ではないかと考えている。
「これまでは建築を発注する側も、受注する建築家なども作ることしか考えておらず、それをどう運用、維持するかを疎かにしてきた。でも、新築が作りにくくなるこれからを考えると営繕は非常に重要。
個人でやるとバックマージンを疑われる場面もありうるので組織にして中立、公平な立場でアドバイスできるようにしていくことが大事だと考えています」
長らく、誰もが大規模修繕一択でそれ以外はないと思い込んできたが、発想を変えることでできること、カバーできるマイナスもあるはずだ。
筆者注:改修、改良、修繕などいくつか同種の多少意味の違う単語があるが、ここではわかりやすさを優先、修繕に統一してある
(出展:2024年4月21日 東洋経済オンライン)
コラム一覧に戻る
